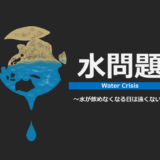留学の3カ国目のケニアでは”Colobus Conservation”という施設でインターンを3カ月していました。
今回はその時の様子について書いていきたいと思います。
“Colobus Conservation”とは

ケニアで2番目に大きな都市Mombasaから南に車で30分程度のところにこの施設はありました。
ケニアで海というイメージはあまり無いかと思いますが、この施設はダイアニビーチという観光地としてとても有名なビーチ沿いにありました。
Colobus Conservationはサルの保護施設です。
この地域には絶滅危惧種の”Angolan Colobus”をはじめとして、5種類のサルが生息していましたが、これらのサルの保護、世話、治療、リハビリ、調査を行っていました。
これに加えて、地元の人への普及・啓発活動やサルの住処となる森林の保護、害獣調査なども行っていました。
また、ここには観光客がたくさん来るため施設内を周るツアーもやっていました。

主な活動内容
・サルの世話
施設には約50頭のサルが飼育されていました。
彼らのほとんどは幼い時に母親とはぐれてしまい、この施設に引き取られた個体です。
これらの孤児は数年間ここで飼育され、トレーニングを受けた後に野生に戻されます。
朝はエサとなる枝を取りに行くことから始まりました。
車で外に行き、道端の木から枝を切り取って施設に持って帰ってきました。
その後、ケージの掃除が始まります。
食べ残しや枝を取り除いて、洗剤とほうきを使ってケージの床と壁を念入りに洗いました。
その後朝に取りに行った枝を入れます。

それが終わったら今度はエサの準備です。
野菜を一つ一つ包丁で切っていきます。
合計で6kgぐらいの野菜を毎日切っていました。
汚れたタオルなどがあったらそれらを手洗いすることも2~3日に1回ぐらいのペースで行いました。

・個体数調査
これは年に2回ほど行われているそうなのですが、今回は自分の滞在期間と運よく同じタイミングでこれに参加することができました。
調査は2週間にわたって行われます。
最初の1週間は”Colobus”、”Cykes”、”Vervet”の3種類のサルの数を数えました。
この施設はダイアニビーチ沿いにあったのですが、このビーチの端から端までおよそ15kmに渡って調べました。
ビーチ沿いには家やホテルがたくさんあるので、その人たちの土地に入らなければいけません。
なので調査が始まる2週間前ぐらいから一軒一軒周って手紙を渡しました。
調査が始まると、僕たちは何チームかに分かれてビーチの端から一つ一つ土地に入ってサルの数を数えていきました。
たまに1匹でいることもありましたが、ほとんどは群れで行動していました。
数を数える他に、「大人♂♀」「若齢♂♀」「子供」「赤ちゃん」などのように分類分けをしなければなりませんでした。
最初はこれがとても難しくて苦戦していたのですが後半になるにつれて慣れていきました。
1日に2万歩ぐらい歩いて疲れました。

次の1週間はヒヒの調査でした。
これは今までとは方法が異なります。
前回はこっちが歩きまわっていましたが、今回はひたすらヒヒが来るのを待っていました。
最初に住民やホテルの従業員にヒヒを見なかったか、最近どこで見たかを尋ね目星がついたところで待機しヒヒの群れが来るのを待ちました。もちろん全然来なかった場合は場所を変えたりしましたが。
1つの群れ辺り40~50頭もいたうえに、今回も大きさや性別で分類分けをしなければならなかったのでとても大変でした。

・レスキュー
怪我をしたサルが見つかると施設に電話がかかってきます。
電話を受けると僕たちは、ケージ、吹き矢、網などをトラックに詰め込んですぐに現場に向かいました。
現場につくと獣医さんが麻酔を用意します。
それを吹き矢に入れてサルをめがけて発射しました。
怪我をしたものの、元気に動き回れるものがほとんどで現場につく頃には逃げていなくなっている場合も多々ありました。
ぐったりしているものはそのまま網やタオルで捕まえていました。

・診療
施設にはとても小さかったですが動物病院があったのでレスキューしてきたサルや、保護しているサルで治療が必要なものの処置をここでしていました。
専属の獣医さんがいてよく一緒に仕事をし、ルームメイトでもあったのでかなり仲良くさせていただきました。
手術も3回ほど見学し、助手をさせていただきました。

・普及・啓発
野生動物を保護するうえで欠かせないのが現地の人の理解です。
Colobus Conservationでは地元の小学生を施設に招いて授業を行ったり、学校の先生向けに植林の講習会をして学校の教育の一環で森林保全活動を促す活動をしていました。
ケニアの海岸沿いおよそ200kmに渡り”Kaya Forest”と呼ばれるユネスコの世界遺産にもなっている森があります。
ここには「ミジケンダ」と呼ばれる先住民が住んでおりこの森を神聖なものとしてあがめており、多くの貴重な動植物が生息しています。
しかし近年は開発が進んだり、若い人たちへこの伝統が受け継がれなくなっています。
Colobus Conservationは現地の人と協力して、学校の生徒にこの森の大切さを広める活動をしていました。

・コンポスト
「コンポスト」とは生ごみや枯葉などの有機物を、微生物の働きで分解させ堆肥にすることです。
これを作るのを手伝いました。
土の中には虫がたくさんいたのですが、僕は半そで、短パン、クロックスで参戦していたので辛かったですね笑
・シードボール
これにはとてもビックリしました。
その名の通りこれは種が中に入っている泥のボールです。
なんと種を埋めなくても、これを投げるだけでその場所に木が生えてくるそうです。
これはサルの生息地保全活動の一環として行われていました。
残念ながら作っただけで、このボールを投げに行くことはできませんでした。

・コロブリッジ
ダイアニビーチには海と平行に長~い道路が1本走っていました。
住民、観光客などが使い、交通量もとても多かったです。
この道路はサルの生息地である森林を切り開いて作ったので、サルがよく道路を渡ります。
容易に想像できるように多くのサルが交通事故に遭い、ケガをしたり死んだりしていました。
僕が滞在しているときも車とぶつかったサルが頻繁に運ばれてきました。
それを防ぐために設置していたのが「コロブリッジ」です。
以下の写真を見ても分かるように、道路の上を通過するようにこのはしごのようなものをかけてサルが道路を渡らないようにしていました。


・罠探し
アフリカの多くの場所では野生動物の密猟が盛んに行われています。
このモンバサも最近はあまり活発でないものの、以前はかなりひどかったそうです。
サルの場合、密猟者は罠を使用します。
なので定期的に林の中に入り罠が無いかチェックしていました。
最近では見つからないことがほとんどだそうです。
僕もこれに1回同行させていただきました。

インターンの生活
・仕事
朝の8時から夕方5時まで働きました。
午前中には10時ごろにちょっとした休憩時間があり、紅茶やコーヒーを飲むことができ、昼休憩は12時から13時でした。
仕事もそんなにきつきつではなかったので仕事の合間に休めることも多くありました。
・休み
週末は片方が午前中だけ働かなければならず、もう片方が丸1日休みでした。
シュノーケリングや、アイランドホッピングなどのツアーもたくさんありましたが、僕はお金を使いたくなかったので行きませんでした笑
ですがそんな僕でもサファリに行ってきました。これは留学に行く前から楽しみにしていましたからね!
多くの野生の動物を見ることができ、ホテルもきれいで大満足でした!

サファリで見た動物についてはここですべて紹介することはできないので以下の記事をご覧ください。
・食事
この施設もタイと同様に料金に食事代、宿代などの滞在費が含まれていました。
料理を作ってくれる専属のスタッフがおり、日曜以外は昼と夜は提供されました。
ウガリ、チャパティなどのケニア料理がほとんど!
お肉を食べる機会は週に数回しかなく、豆中心の食生活でした。
とても美味しいというわけではなかったですが、お腹いっぱい食べることができましたし、何より現地の食生活を経験することができたので良かったです。
日曜日の昼は外食していました。
外食と言っても道端にある屋台での食事です。
100~150円くらい払えばお腹いっぱいになりました。
上でも述べたようにここは観光客がたくさんいるのでちゃんとしたレストランもたくさんあり、たまに行っていました。

・部屋
部屋は3つありました。
僕は1番大きな部屋でケニア人4人ぐらいとの生活です。
部屋にはベッド4つに二段ベッドが1つと合計6人滞在できました。
また、クローゼットがついており、バスルームも部屋の中にありました。
部屋とバスルームは毎日掃除してくれるスタッフさんがいてきれいだったのですが、ここはケニアなので虫がたくさん!
特にバスルームには”G”がたくさんいてシャワーを浴びているときに出たときは最悪でした。
ですがここでの1番の敵は「蚊」。
日本ではあまりなじみが無いと思いますが、アフリカの蚊はマラリアという病気を媒介します。
寝ているときに刺されないように、全てのベットには蚊帳がありました。
ですが、穴があったり、肌とネットが触れたりしていたので毎晩何カ所か刺されていましたが…
あとはケニア人とのルームシェアも少し大変でした。
今までこんなにアフリカの人に囲まれて生活することなんてなかったので、最初の方はかなり緊張しました。
みんな日本字の僕に親切で1週間ほどですぐに溶け込めましたが、夜中まで大声で電話したり、イヤホン無しで動画を見られたりするのには最後まで慣れませんでした…


・洗濯
ケニアでは一部の人しか洗濯機を持っておらずほとんどが手洗いでした。
ここでは汚れた服を洗濯かごに入れると、掃除のスタッフさんが手洗いで洗ってくれました。
下着は自分で洗わなくてはいけなかったので、自分で手洗いしていました。
お金について
| 週 | 金額(円) |
| 2 weeks | 71,500 |
| 3 weeks | 82,500 |
| 4 weeks | 110,000 |
| 5 weeks | 137,500 |
| 6 weeks | 159,500 |
| 7 weeks | 181,500 |
| 8 weeks | 203,500 |
| 9 weeks | 225,500 |
| 10 weeks | 231,500 |
| 11 weeks | 247,500 |
| 12 weeks | 264,000 |
ここも働くのにお金を払わないといけません。
僕は1日当たり3,200円ほど払った計算になるのですが、意外と妥当な値段なのかもしれません。
Q&A
特に質問受けたことはありませんが勝手に予想して作ってみました!
Q 施設にはどうやって行きましたか?
A 最寄りの空港のモンバサ空港まで迎えに来てもらいました。
モンバサ空港が施設から車で1時間半ほどの場所にあるのですが、来る時と帰る時の送迎は施設がしてくれて、これは料金に含まれていました。
Q 治安はどうでしたか?
A 良かったです。
観光客も多くいいましたし、治安はかなり良かったです。
滞在した3カ月で自分が何かに巻き込まれることもなく、大きな事件も聞くことがありませんでした。
ですが、夜に出歩いたり、大金を持ち歩くということは決してしませんでしたが。
Q 感染症などは流行していましたか?
A マラリアがとても怖かったです。
ケニアの中でもこのモンバサという地域はマラリアの流行地らしくかなり警戒してました。
マラリアの予防薬を買って毎日飲んでいたので幸いにもかかることはありませんでしたが、毎日のように蚊に刺されていたのでいつかかってもおかしくない状況だったと思います。
マラリアの予防薬が1錠590円もしてそれを3カ月毎日飲んでいたので、出費がすごかったです…
あとはエイズもかなり流行っているそうです。
アフリカなので狂犬病もあったかともいますが、現地の人に尋ねても聞いたことが無いとのことでした。
↓↓マラリアについては以下の記事でまとめています。↓↓
Q 現地での生活は日本とは違いますか?
A 日本での生活に慣れていると大変かもしれません。
僕はフィリピンとタイで日本とは全く違う生活をすることには慣れていましたが、そんな僕でも最初は少しきつかったですね笑
蚊やハエ、蛾などは当たり前で、大きなムカデが部屋に出てくることもあり、1回枕の下にいたときは本当に焦りました。
それらは全然大丈夫なのですが、”G”だけはどうしても無理で出た際はルームメイトに助けを求めていました。
あとは水道水が飲めないのは当たり前で、シャワーは温かいのが使えたのですがなんと水がしょっぱかったです。
現地の人に聞いてみると、海に近くなるにつれ水道水がしょっぱくなるとか…
3カ月で合計10人位のインターンと出会ったのですが、その内2人は来た次の日に帰り、1人は数カ月いる予定だったのにたったの3週間で帰ってしまいました。それなりの覚悟が無いとここでの生活は厳しいと思います。
Q 何語を話していましたか?
A ずっと英語です。
ケニアは公用語が英語で、学校でも国語(スワヒリ語)以外の授業は英語で行われます。
なので皆さん話すことができ、高学歴の人の英語は完璧でした。
僕と話すときはもちろん英語なのですが、スタッフさん同士が話すときはスワヒリ語メインで話すことも多々ありました。
インターンで、アメリカ人、イギリス人、スウェーデン人、デンマーク人もいたのでいい英語の勉強になりました。
Q ケニアはプラスチック袋が使用禁止と聞いたことがあるのですが本当ですか?
A 本当です。使用が見つかると罰金または懲役となります。
ケニアでは2017年からプラスチック袋の製造・販売・使用が禁止されています。
僕が服を入れるのにプラ袋を使っていたのですが、それを見た同僚に「外には絶対持っていくなよ」とくぎを刺されました。
一番驚いたのはゴミ箱です。
ゴミ箱に袋をかぶせることなくそのまま入れていました。
生ごみは水気があるので漏れないように普通はプラ袋にいれますが、ここでは段ボールにそのまま入れていました。
町に出かけても皆さん袋を持参しており、プラ袋を見ることはありませんでしたね。

ケニアは日本から遠く離れていますし、病気・治安などの不安からあまりいいイメージを持っていない人が多いかもしれません。
しかし、「日本と違う」ということは日本では味わえない新しい経験をたくさんできるということです。
動物好き、特に野生動物好きの人にとってはとてもおすすめしたい国です。
もしケニアに行く機会があれば数週間ここで”Team Colobus”の一員としてサルの保護に貢献するのもいいのではないでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました(^^)